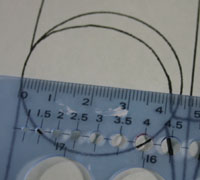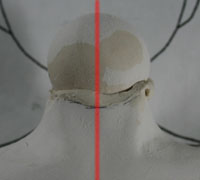実際に作った手足とのバランスも考慮して作っていって下さい。
芯に使う発泡スチロールは10、12、15、20、25、30、40ミリがあれば
60センチ程度の人形には間に合います。
2〜5ミリ刻みですが、意外とこの差が大きいので、
以上のサイズは揃えておくと良いと思います。
あとあまり沢山球を作るとか、とても大きな球を作るのでしたら
型を取って作ってしまった方が楽だと思います。
発泡スチロールから球を型取りして作る方法はリンク先の虎目式人形庭園
で紹介されています。素人でもお手軽にできそうですし、便利そうです。